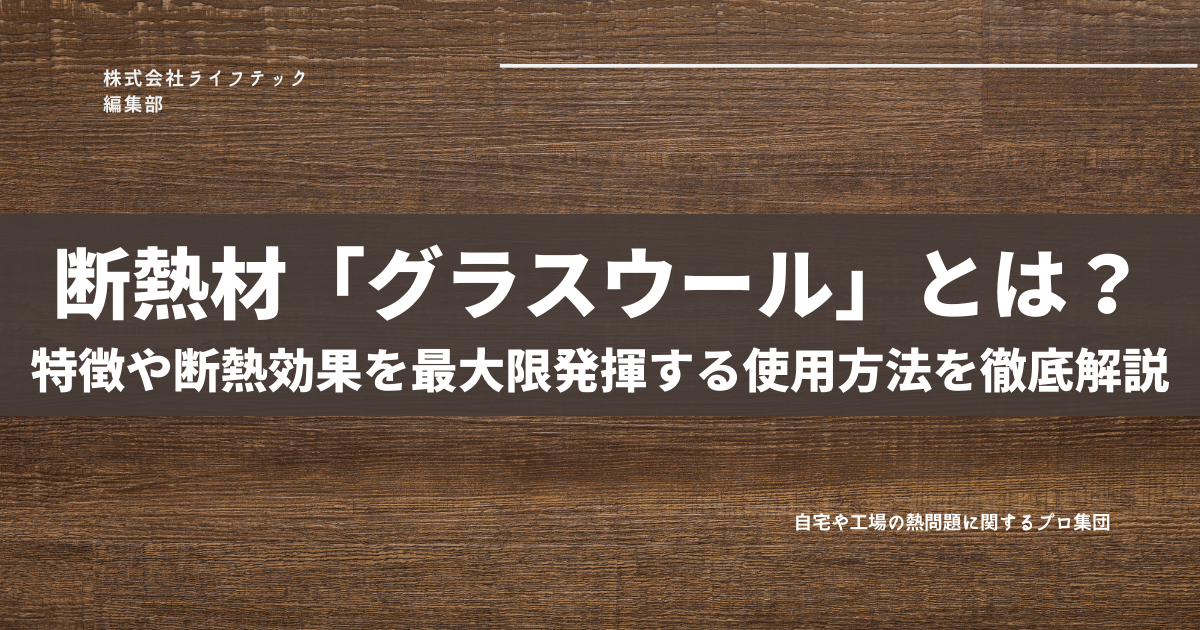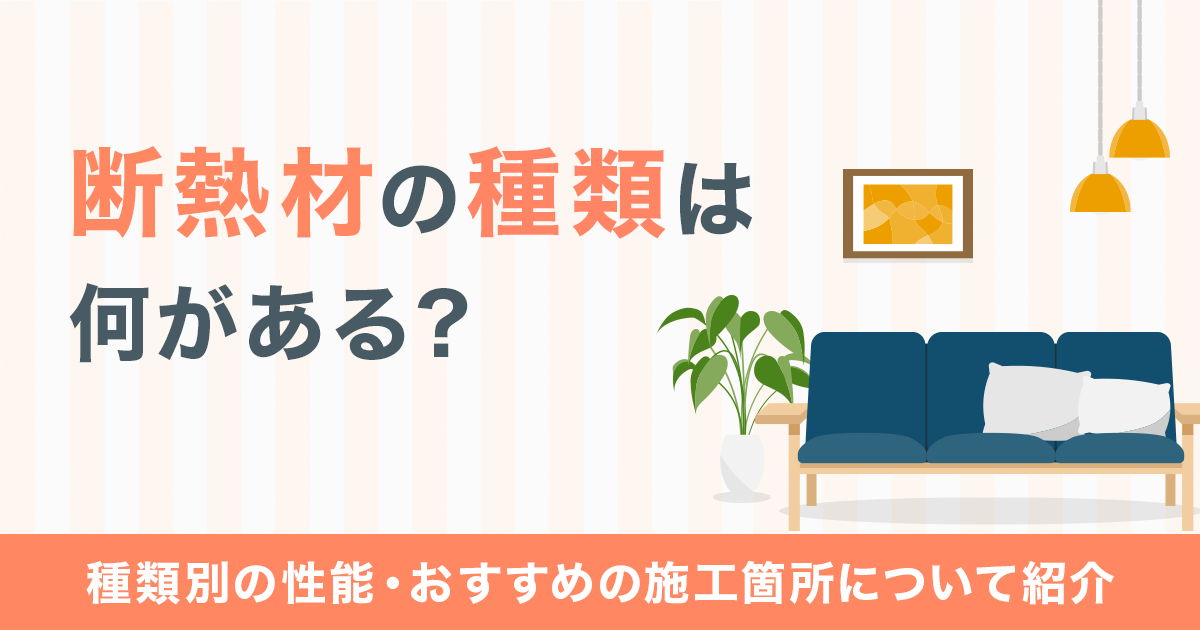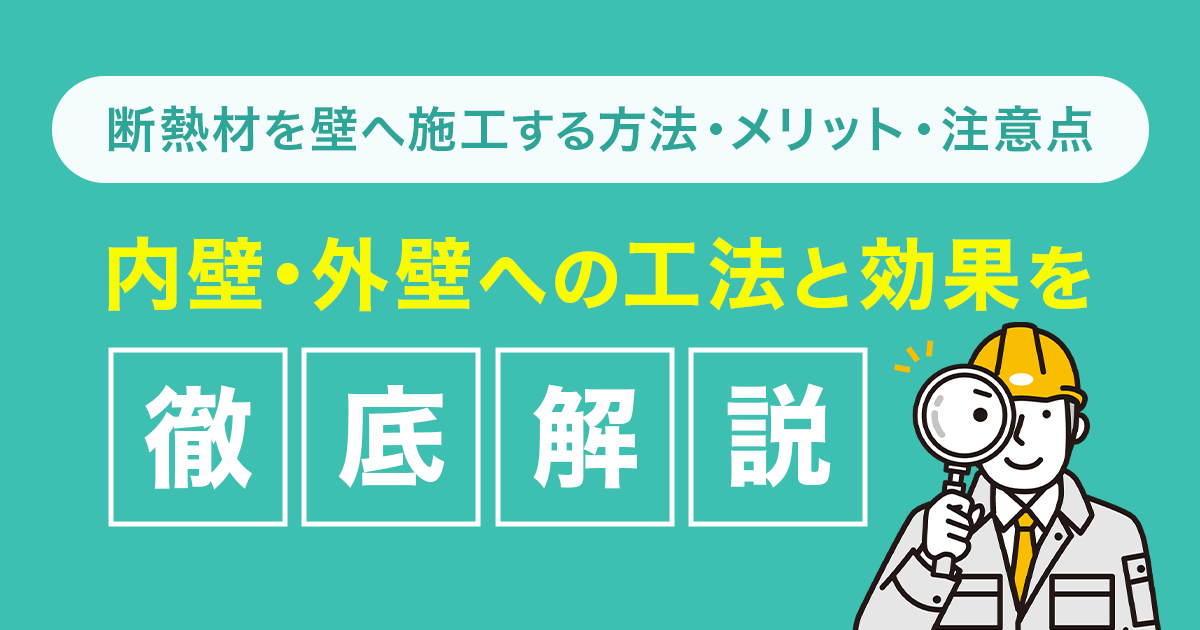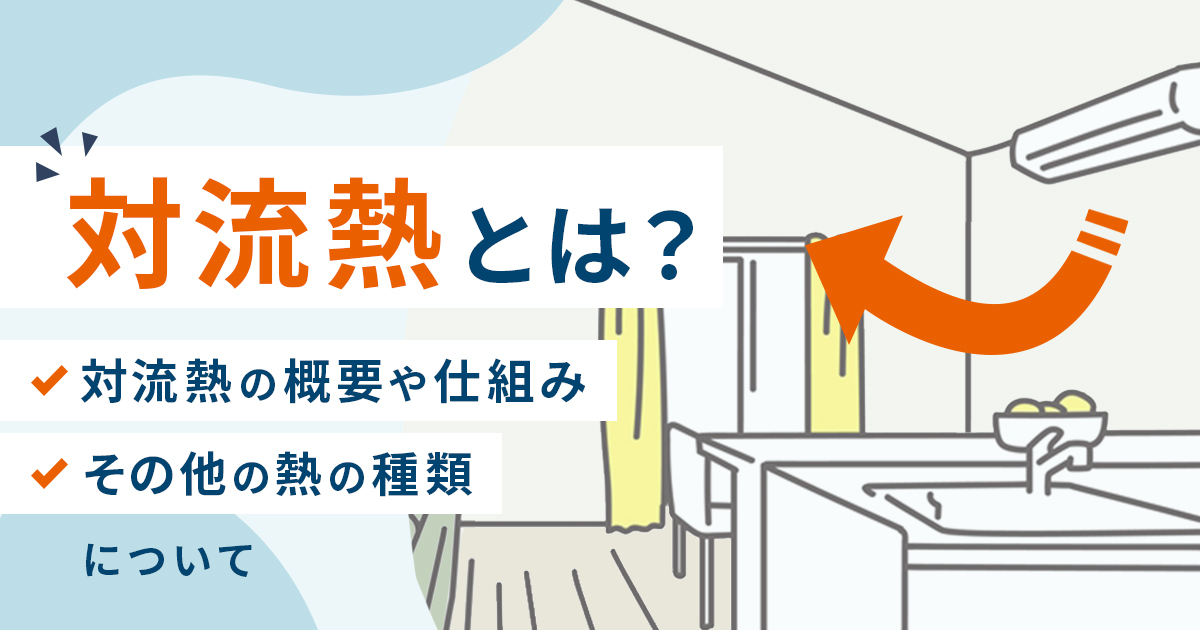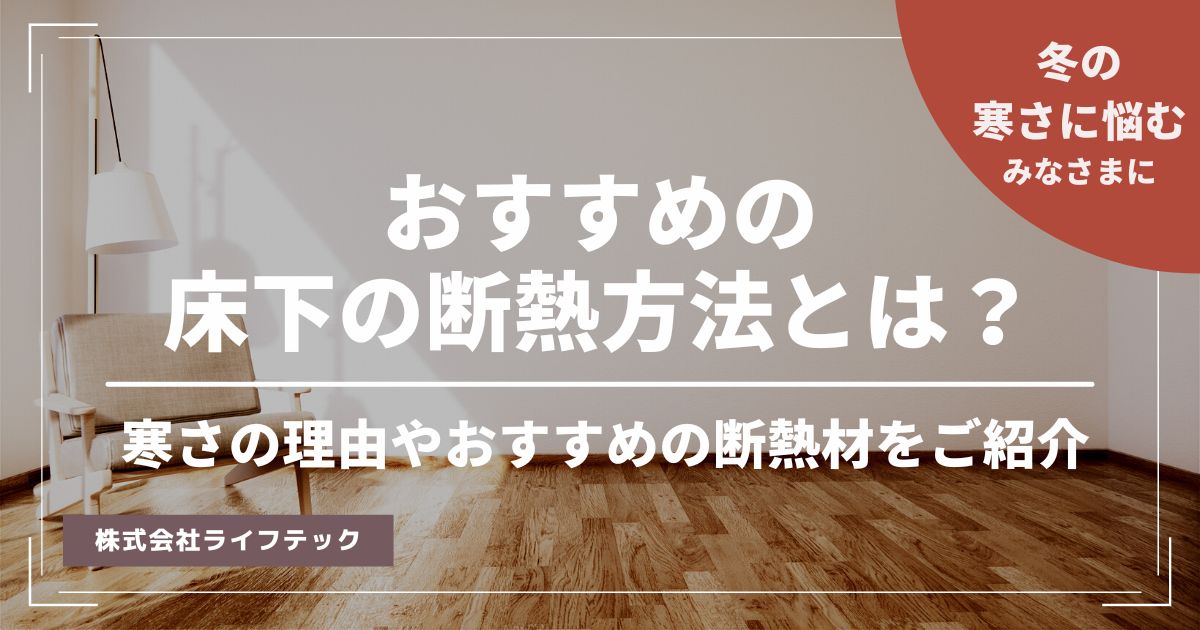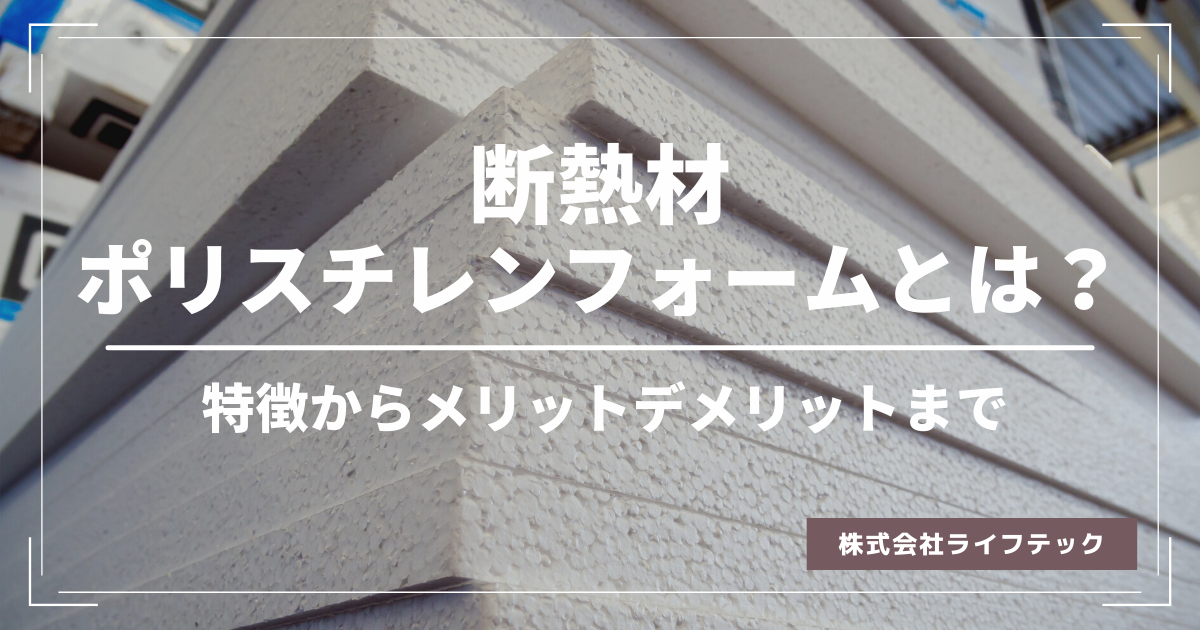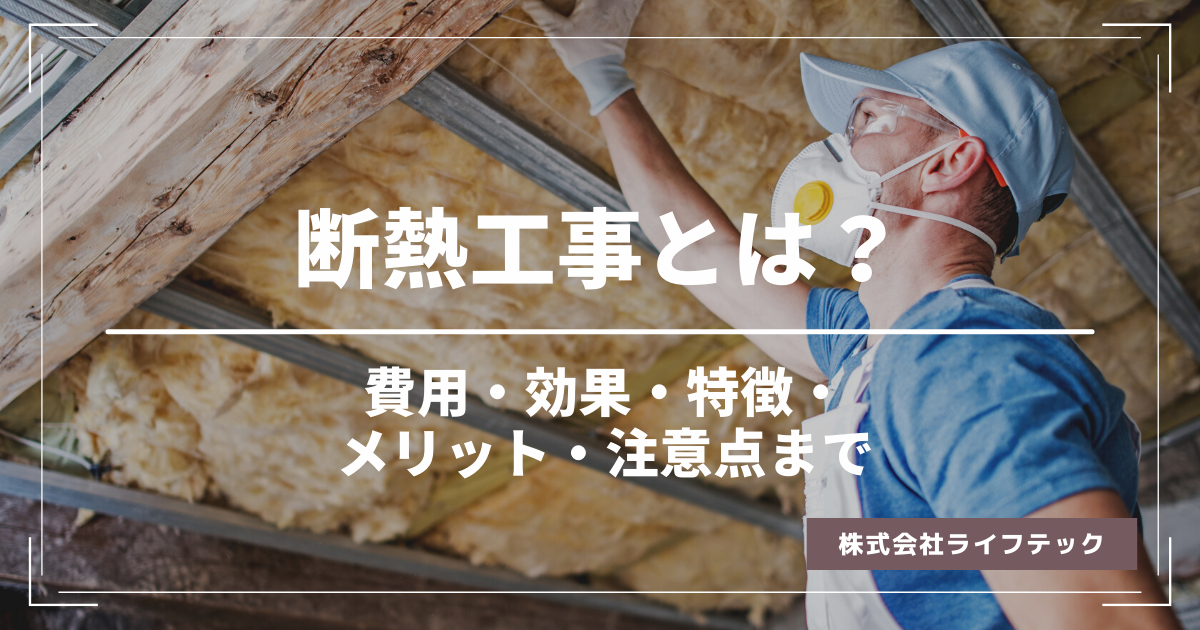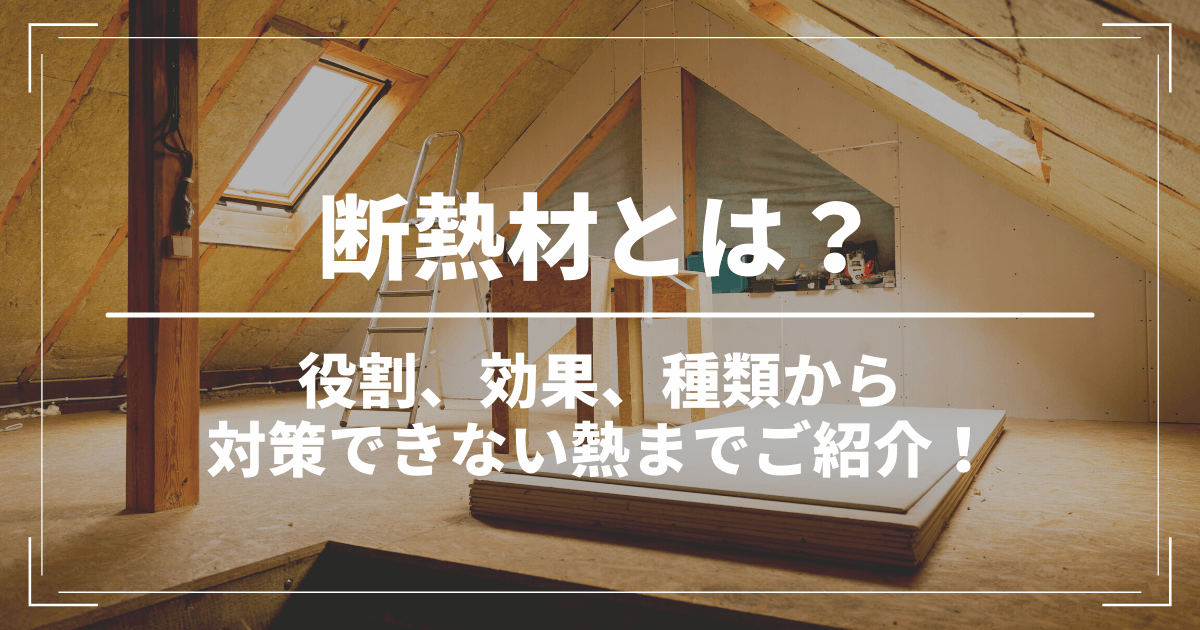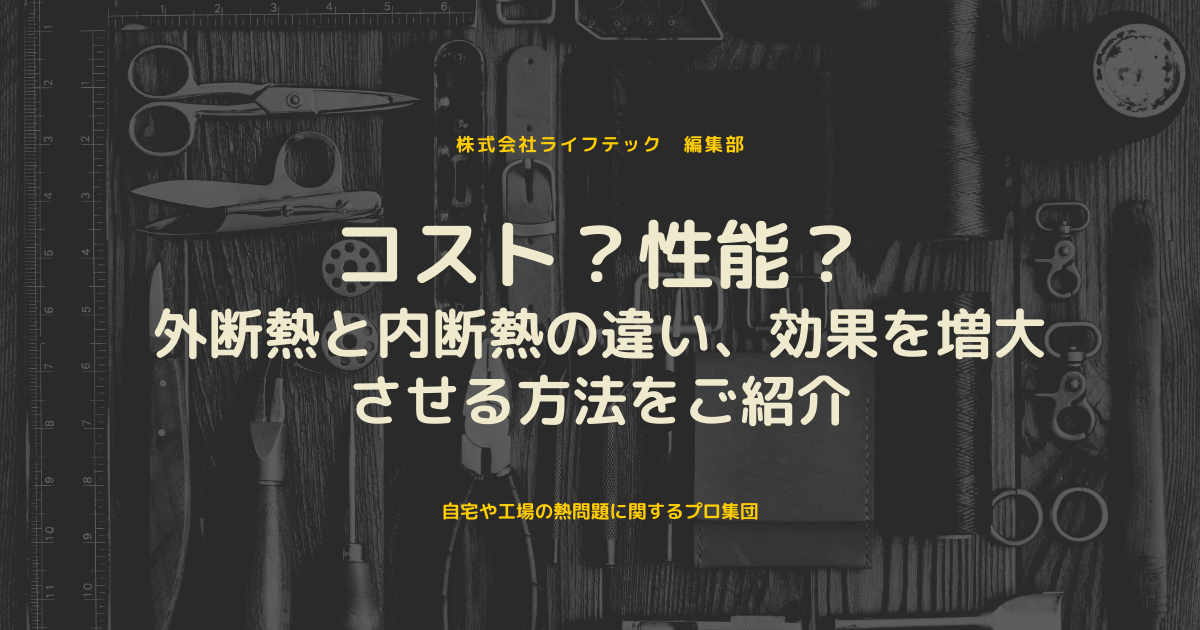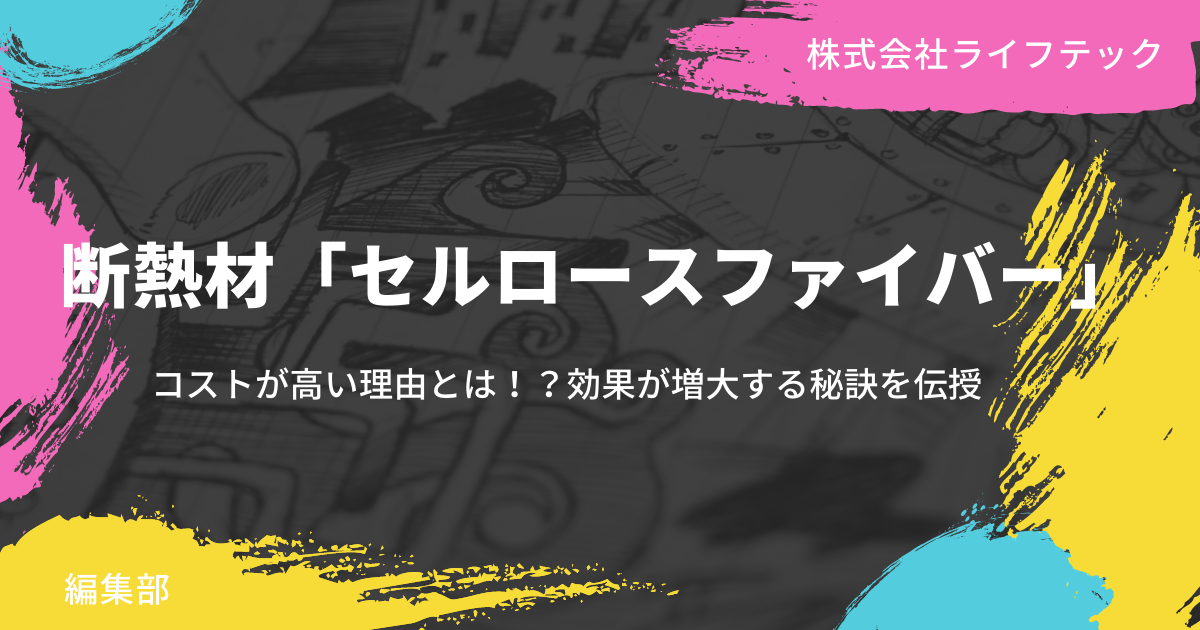よく耳にする「グラスウール」という断熱材をご存知ですか?断熱材は、正しく使用しないと断熱効果は発揮されません。この記事では、グラスウールの特徴やメリット、断熱効果を増大させる有効な使用方法について詳しく解説していきます。
そもそも、断熱材とは?という方はぜひ以下の記事も合わせてご確認ください。
断熱材グラスウールとは?
断熱材 グラスウールとは、ガラス繊維を綿状に固めた断熱材です。断熱材=グラスウールと言われるほど、多くの住宅に採用されています。細かい繊維と繊維の間に空気の層を作ることで、断熱性能を発揮することが可能です。また、グラスウールは「10K」「32K」といったようにグレードが存在します。こちらは断熱材の密度を表しており、数字が大きいほど高密度で断熱性能が高いです。
グラスウールのメリット
グラスウールは、他の断熱材と比べてコストが安いです。施工する際、ウレタンフォームなどと違い専用の機械が必要ないので、施工にかかるコストを削減できます。以下の表をご覧ください。施工にかかるコストを他の断熱材と比較したものです。
| 断熱材 | 一棟当たり(万円) |
| グラスウール | 25〜30 |
| ロックウール | 25〜30 |
| セルロースファイバー | 95〜120 |
| 羊毛断熱材 | 50〜60 |
| ポリエステル断熱材 | 50〜60 |
| ポリスチレンフォーム(押出) | 50〜65 |
| ポリスチレンフォーム(ビーズ法) | 50〜65 |
| ウレタンフォーム(ボード) | 70〜80 |
| ウレタンフォーム(吹付) | 65〜75 |
| フェノールフォーム | 70〜80 |
1棟当たり:延床面積が40坪の家を施工した場合の断熱材の価格
グラスウールは施工性にも優れており、床や壁、天井など使用用途は様々です。材質上、カッターを使って大きさを調整することも可能です。またグラスウールはガラス繊維が主原料であるため、シロアリの被害を受けにくいというメリットもあります。
グラスウールのデメリット
グラスウールは湿気に弱く、雨漏りや結露により水分を含むと断熱効果が著しく低下してしまいます。さらにグラスウールは乾燥しにくいという特徴があります。一度水分を含むとカビが発生し、建物の劣化に繋がっていきます。そのため、湿気による断熱効果の低下や建物の劣化を防ぐために、気密性を高くしたり、防湿するといった工夫が必要です。
グラスウールの有効的な使用方法
グラスウールは、綿のように柔らかいので壁の中や天井の上などの空間に充填する施工方法が最も適しています。さらに遮熱材と併用することで、グラスウールだけでは防ぐことが難しい輻射熱を遮熱材が止めるので断熱効果が大幅に上がります。
輻射熱に関しては「輻射熱(放射熱)とは?対策方法から特徴までをわかりやすく解説」以下のページで詳しく解説しております。
遮熱材との併用方法
ここからは、遮熱材と併用して使用する方法をご紹介します。まず前提として、グラスウールを遮熱材と密着するように施工します。天井の場合はグラスウールの上に遮熱材を設けると効果的です。壁の場合はグラスウールの外側に遮熱材を設けることで、夏の暑さに対して効果が発揮されます。床の場合は断熱材の上部に遮熱材を施工します。
遮熱材のメリットやデメリットについては「遮熱シートのメリットとデメリット|デメリットを解決する方法も徹底解説!」の記事で詳しく解説しております。こちらも合わせてご確認ください。
まとめ
グラスウールは安いだけでなく、施工性や防蟻性にも優れています。さらに遮熱材と併用することで、断熱効果がかなり増大します。しかし防湿がされていなかったり、気密性が低いと、水分を含んだ際にすぐダメになってしまうので注意が必要です。グラスウールの断熱効果を最大限発揮できるように使用しましょう。